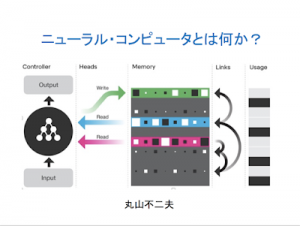人工知能の歴史を振り返る
2017/07/31 マルレク「人工知能の歴史を振り返る 」概要
2012年に、研究者とIT業界の中で「ディープラーニング」のブームが起きてから、5年がたとうとしている。
現在では、人工知能技術が、我々の生活と未来にとって大きな意味を持つだろうことに、研究者やIT業界の枠を超えて、多くの人たちが関心を持ち始めている。そのことを反映して、メディアでも、5年前とは比較にならないほど、多くの情報が流れている。ただ、それらの全てが正しいものだとは限らない。
「人工知能には、今、何ができて、何ができないのか?」「人工知能は、これから、どのように発展するのか?」現在の到達点を知り、未来を予測するには、歴史を振り返ってみるのが有効だと、僕は考えている。
人工知能の歴史は、コンピューターの歴史とともに古い。「Computer=計算機=計算する機械」の登場は、機械の歴史上の画期をなすものなのだが、それが「計算する機械」以上の可能性を持つことに、気づいた人たちがいる。
20世紀には、人工知能研究の多様な試みがなされた。そこでの問題意識・開発されたフレームワークのいくつかは、試行錯誤を繰り返しつつ、21世紀の人工知能技術に引き継がれている。
よく知られているように、今日のディープラーニング技術は、Perceptron -> PDP/Connectionism -> Deep Learningと続く、ニューラル・ネットワーク技術の直系の子孫である。
21世紀、計算機のパワーの増大・グローバルなネットワークの成立・データの爆発的増大は、人工知能研究に新しい環境と可能性を与えた。
人工知能研究に、「歴史上、成功した唯一の方法」があるわけではない。人工知能研究のアプローチが多様であることは、人間の知的能力の複雑さを反映している。
現時点で「人工知能」の限界として意識さるべきものは、決して解かれることのない謎ではない。それは、正確に、我々「人間の知能」の到達点をさししめしていると考えられる。なぜなら、人工知能を作ったのは我々人間であり、機械の進化にとって、我々は「万能の創造主」に他ならないのだから。
「人工知能には、今、何ができて、何ができないのか?」「人工知能は、これから、どのように発展するのか?」という機械の知性についての先の問題は、 「人間には、今、何ができて、何ができないのか?」「人間は、これから、どのように発展するのか?」という人間の問題に投げ返されることになるだろう。
はじめに
講演資料 (ダウンロード)
Part I 20世紀 (過去)
TuringとChomsky
「機械は考えることが出来るか?」という問題を、始めて提起したのはTuringである。その問題意識は、画期的なものだ。Chomskyは、Church-Turingらが行った仕事(計算可能性・帰納的関数論)にインスパイアされて、文法の形式的記述を目指す。
Simonの楽観論
Simonは、人工知能の未来を楽観視していた。それは、経験論的で、ヒューリスティックな問題解決のスタイルが万能だと信じていたからである。ただ、それはうまくいかなかった。
一方、同じ頃、Chomskyは合理論の立場から、刺激(Stimulus)ー反応(Reaction)のS-R図式で、心理学を基礎づけようとする「行動心理学」を徹底して批判していた。
パーセプトロン
Rosenblattのパーセプトロンは、現在のニューラル・ネットワークの最初の起原にあたる。日本の福島邦彦の仕事も、ニューラル・ネットワーク技術に影響を与えた。パーセプトロンの限界を指摘したのは、Minskyである。
論理的推論能力
Simonが開発した自動証明のプログラムLogical Theoristは、命題論理において貧弱な証明能力しか持たなかったが、これらの問題を解決したのが、Robinsonである。
彼が開発した Resolution/Unificationの手法は、後の論理型言語のPrologやGHC、さらには証明支援システムであるCOQ・AGDA等の基礎となった。
懐疑論
50年代末から60年代の初めにかけて優勢だった、人工知能の可能性についての楽観論は、成果をだせないまま影をひそめた。かわって、70年代には、人工知能についての懐疑論が広がった。
講演資料 Part I (ダウンロード)
Part II 21世紀 (現在)
大規模分散システムと検索技術
21世紀のIT技術を特徴付けるのは、検索と広告にドライブされた大規模分散システムの成立である。
文字列検索から知識検索への移行は、まだ、始まったばかりである。ただ、その枠組みを提供しているschema.org等のEntity Modelは、貧弱なものだ。
言語学の新しい展開
Chomskyは、言語学に新しい枠組みを提案している。
基本的に、計算システムとして言語能力を再構築しようというもので、人工知能技術とは相性は悪くないのだが、AI研究者はあまり興味を持っているようには見えない。
一方、こうした言語理論に基づく、実際の計算システムの構築は、大きく遅れている。それでは、説得力を持てない。
Deep Learning
2012年以降、ニューラル・ネットワークを用いるディープラーニングの手法が、AI研究を飲み込んだように見える。これは、技術史上でも稀なパラダイム・シフトが進行したことを意味する。ただ、こうした突然の変化に、皆が追従できているわけではない。また、一つの方法論で、人工知能の課題が全て解決できるわけでは無い。
人工知能技術の現在
人工知能技術の現在の到達点は、機械が眼と耳と口を備え、自律的な運動能力を獲得しつつあると捉えるのがわかりやすいと思う。ただ、それは、人間を含めて、多くの生物が進化の過程で獲得してきた能力に他ならない。
他の生物には無い、人間固有の知的能力の機械での実現を、人工知能技術の目標と考えるのなら、我々は、まだそのスタート地点に立っているだけである。
講演資料 Part II (ダウンロード)
Part III 未来展望
Real とは何か?
人工知能の未来の展望を語る前に、ここでは、僕が誤っていると考えている認識の理論を紹介しよう。
それは、「Realとは、脳によって解釈された電気信号に過ぎない」という認識像である。
人間の感覚能力の外的拡大
機械が、生物のように、目や耳といった感覚器官を備え始めたというのが、現在の人工知能技術の一つの到達点であるなら、我々人間も、他の生物にはない感覚器官を、新たに備えつつあると考えることができる。そうした人間の感覚能力の外的拡大は、機械によって初めて可能となった。
未来の人工知能は、こうして新しく人間が獲得した能力も、取り込まなければならない。
人間の認識能力の数学的認識による拡大
人間は、感覚能力を外的に拡大しただけでなく、他の生物にはない、特殊なやり方で外界を認識する。一つは、言うまでもなく人間のみが持つ言語能力に基づく対象の把握なのだが、もう一つは、数学的な認識に基づく自然の認識である。
数学的認識能力は、シンボルを操作する言語能力を基礎とするのだが、それには還元できない独自の能力である。言語能力が解明されるべき多くの謎を持つように、数学的能力も謎が多い。
人工知能研究のパースペクティブ
ここでは、人間の認識能力の発展と、歴史的に形成されたその階層について考えてみる。これらの諸階層に対応した人工知能技術が、本来、必要となる。
現状を見る限り、弱い環があるのは明らかなのだけれど、それを直ちに埋めることは容易では無いのかもしれない。
ただ、それは、けっしてペシミスティックな展望ではない。研究すべき多くの課題があるということは、むしろ好ましいことだと僕は考えている。